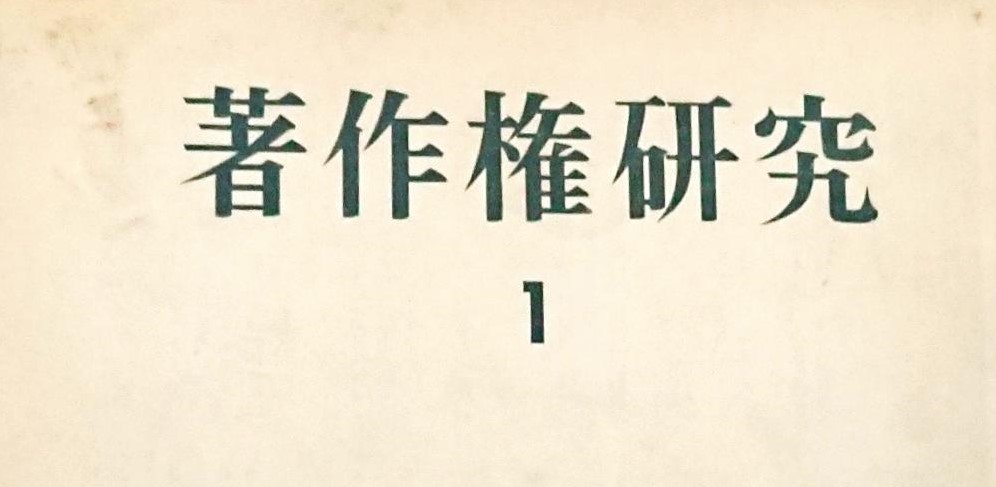はじめに
リーガルテックには様々なものが存在するが、その中で、業種を超え、どの企業の法務部にとっても、とっつきやすいのは、契約業務に関するものであろう。そのため、電子契約システムを、既に導入した企業、導入を検討している企業は、少なくないと思う。
電子契約に関しては、その有効性、ハンコに代わる電子署名の効力、裁判での扱いなど、民法・民事訴訟法・電子署名法などに関する様々な問題について、既に多数の検討がなされてきたところであり、本稿で、それらの点について改めて立ち入るつもりはない。
ただ、著作権法の研究者として、素直に疑問に思うのは、他の分野で、電子化=デジタル化と言えば、いつも問題となる、著作権に関しての議論をほとんど見かけないことである。契約(書)の電子化=デジタル化に際して、著作権法上の問題は生じないのであろうか? 本稿では、この点について、まずは入り口となる著作物性に関して、若干の考察を行おうと思う。もっとも、お読みいただければ分かるように、あまり実益のある議論ではないので、あくまでも「夜ばなし」です・・・(^^;)
本当は「夜話」とすべきなんだろうけど、ブラック・ジャックの「雪の夜ばなし」にならってみた。ちなみに「雪の夜ばなし」は、こんなお話し。
1 そもそも著作物か
1-1 著作物の定義
検討のスタートは、やはり、契約書や各条項(以下、契約書等)が著作物かどうかであろう。契約書等の著作物性が否定されれば、デジタル化云々に関して、著作権法上悩む必要はなくなる。
契約書等が、著作物に該当するかどうかは*1、著作権法の「著作物」の定義に照らして判断する必要がある。著作権法2条1項1号は「著作物」を
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
と定義している。この定義は、
- 思想または感情の表現であること
- 創作的な表現であること
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属する表現であること
に分解することができる。順にみていこう。
1-2 第1要件
契約書等の著作物性について論じる際に、((よく参照されるのは))、「船荷証券用紙」事件である。この事件では、原告が被告から依頼を受けて、被告が取引先との間で使用する船荷証券の用紙を作成して納入したところ、後に被告が原告以外の印刷会社に前記用紙を複製させていたため、複製権侵害などが問題になった事案である。判決(東京地判昭和40年8月31日判時424号40頁)は、
「著作物とは、精神的労作の所産である思想または感情の独創的表白であつて、客観的存在を有し、しかも文芸、学術、美術の範囲に属するものと解されるところ、前記認定のように、本件ビー・エルは、被告がその海上物品運送取引に使用する目的でその作成を原告に依頼した船荷証券の用紙である。それは被告が後日依頼者との間に海上物品運送取引契約を締結するに際してそこに記載された条項のうち空白部分を埋め、契約当事者双方が署名又は署名押印することによつて契約締結のしるしとする契約書の草案に過ぎない。本件ビー・エルに表示されているものは、被告ないしその取引相手方の将来なすべき契約の意思表示に過ぎないのであつて、原告の思想はなんら表白されていないのである。従つて、そこに原告の著作権の生ずる余地はないといわなければならない。」
と説示した。
この判決は、旧法に関するものであるが、冒頭の説示から明らかなように、著作物の定義としては、現行法のそれと実質的に同一のものとなっている。その上で、現行法の定義で言えば、第1要件が満足されないことを理由として、船荷証券用紙の著作物性を否定している。
ただ、船荷証券の著作物性を否定した結論には同意可能としても、その論理には首をかしげざるを得ない。
判決は、問題の船荷証券の用紙は「契約書の草案」つまりひな形であって、それによって交わされるのは契約当事者の「将来なすべき契約の意思表示に過ぎ」ず「原告(筆者注:ひな形作成者)の思想は何ら表白されていない」とする。すなわち、ひな形を作る段階で、原告は、被告が将来(そのひな形を利用して実際に取引を行う際に)表示するであろう意思を、被告の代わりに表現しているから、原告の思想・感情はそこには存在しないというのである。
しかしながら、そもそも、著作物の定義規定は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とするだけであり、表現は著作者自身のものであることは求められているが(創作的=originalとはそういうことである)、表現される思想・感情が著作者自身のものであることまでは求めていない。
例えば、Aが発案した物理学の理論を、Aから学んだBが、B自身の言葉で文章にする場合を考えてみて欲しい。この場合、出来上がった文章は、Bの著作物であろう。その文章によって伝えられる内容が、Aによって発案されたものであるということは、この文章の著作者がBであることに何ら影響しない*2。
よって、ひな形に表現されている思想・感情が、原告のものではなくて、被告(とその取引先)のものだからという理由で、著作物性を否定するのはおかしいということになる*3。
ただ、そもそもの問題として、前記ひな形には、被告らの思想・感情しか存在しないという理解は、本当に正しいのだろうか。例えば、先の例の場合、Bが記した文章には、Aの思想・感情(Aが発案した物理学の理論)が表現されているが、同時に、Bの思想・感情(Aの理論を具体的にどのように表現しようかという考え・思い*4も表現されていると言えるのではないだろうか。Aの理論を、Aが語った言葉どおりBが文章化した(典型的には口述筆記した)のでない限り、出来上がった文章には、Aの思想・感情だけでなくBの思想・感情も存在するはずである。同様に、問題のひな形にも、通常は、被告と取引先との思想・感情だけでなく、原告の思想・感情(被告と取引先との思想・感情をどのようの表現しようかとする原告の考え・思い)が存在するはずであろう。
仮に、以上のような理解に基づいて、本判決を善解するとするならば、本判決は、原告が、被告から命じられるまま何の工夫もせずに、ひな形を作成したと捉えていたので、ひな形には「原告の思想はなんら表白されていない」と述べたことになろう*5。ただ、残念ながら、判決が認定した事実関係からは、そのような事情は伺えない。そういう意味では、本判決は、一つの著作物中に複数の思想・感情が、複層的に併存しうることを理解できていなかったということになりそうである。
1-3 第2要件
船荷証券事件の場合、(1-2でみたように)船荷証券のひな形に、原告の思想・感情が表現されていたとしても、それが創作性のある対象で表現されていなければ、著作物性は否定される。そういう意味では、同事件は、第1要件の問題としてではなくて、第2要件の問題として検討されるべきであったろう*6。
契約書等においては、その性質に照らして考えると、そこに定めるべき取引に関する様々な事項(いわゆる、商流・金流・物流・人流など)を、正確かつ簡潔・明瞭に、そして法令等に合致するように記載しなければならないので、具体的な表現の選択肢は限られたものとなり、表現の創作者が個性を発揮する余地は限定され、創作性が認められるケースも限られてくるだろう*7。結果、一般的な取引であるために、記載すべき事項が一般的に見られる内容とほとんど異ならない場合は、作成された契約書等の表現は、多くの場合、ありふれた表現となり、創作性は否定されるだろう。
取引自体がユニークな場合は、契約書等の表現もユニークなものとなろう。ただ、ここで注意しなければならないのは、ユニークなアイデア(ここでは取引)を個性なく表現している場合を、創作的な表現と見誤らないことである。あるユニークなアイデアを、契約書等の性質上必須の、正確・簡潔・明瞭・遵法的に表現する方法が限られている場合は、そのような表現は、なお創作性のない表現とされなければならない。ユニークなアイデアの表現であるため、従来、それが表現されたことはないため、厳密な意味では「ありふれた」表現とは言えないかもしれないが、その場合も、仮に、過去にそういうアイデアが登場しそれが表現されていたとするなら、一般的に同一・類似の表現となっていたであろうと考えられるような場合は、なお、ありふれた表現と捉えるべきであろう*8。
つまり、契約書等については、その性質に照らして、創作性が否定されることが多いと思われるものの、逆に、ありふれていない表現、ありがちでない表現については、創作が認められる余地があるといえる*9。
裁判例を見てみると、修理規約事件判決(東京地判平成26年7月30日平25(ワ)第28434号)では修理規約の個々の条項については、創作性なしとして著作物性を否定している。例えば、
以下の場合には、保証期間内であっても有償修理となります。
1 落下・衝突等の衝撃、浸水、火災や地震等天変地異による故障・破損
2 外装部品(リューズ・プッシュボタン・針・文字盤含む)及びゼンマイについての切断・損傷等の不具合
3 当社以外での修理又は改造による故障・不具合
4 修理箇所とは別の箇所を原因とする故障
5 当社で発行する修理明細書のご提示がなく、当社による修理が確認できない場合配送時に生じた故障・破損
6 不適切な取り扱いによって生じた故障・破損
以上の原告規約文言5については、
原告規約文言5は,保証期間内であっても有償修理となる場合を例示するというありふれた表現で規定したものにすぎず,例示として掲げられた各項目についても実際に有償修理となる具体例を事実として掲げただけであるから,創作的な表現とはいえない。
と判断している。また、
当社及び関連会社はお客様と対等な立場で、当社の最善の修理及びご対応をさせていただきます。いかなる場合であっても、本修理規約に定めのない値下げ、賠償、再修理その他一切の要求に応じることはありません。特に悪質な場合には、速やかに当社顧問弁護士と相談の上、しかるべき措置を取らせていただきます。
以上の原告規約文言56については、
原告規約文言56は,注文者と対等な立場で,最善の修理を行い,対応すること,規約に定めがない一切の要求に応じないこと,悪質な場合には顧問弁護士と相談の上,措置を検討するということについて,ありふれた表現で規定したものにすぎず,創作的な表現とはいえない。
と判断している。
ただ、この判決では、修理規約の個々の条項ではなく、修理規約全体については
一般に,修理規約とは,修理受注者が,修理を受注するに際し,あらかじめ修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」,すなわち条文や箇条書きのような形式で文章化したものと考えられるところ,規約としての性質上,取り決める事項は,ある程度一般化,定型化されたものであって,これを表現しようとすれば,一般的な表現,定型的な表現になることが多いと解される。このため,その表現方法はおのずと限られたものとなるというべきであって,通常の規約であれば,ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる。
しかしながら,規約であることから,当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく,その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には,当該規約全体について,これを創作的な表現と認め,著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべきである。
と述べた上で、「疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点・・・において,原告の個性が表れている」として、その部分に限り著作物性を認め、被告の規約がその部分も共通していることをもって、著作権侵害を認めている*10。
規約の著作物性が認められたこと自体は注目に値するが、一方で、「同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述する」というのは、規約や契約に於いて必ずしも望ましい表現方法とは言えず、むしろ避けられる傾向もあるだろうことを考慮すると、一般化するのは難しい判決ということができよう。
1-4 第3要件
契約書等に関して、第3要件の該当性について、特に問題になることはないだろう。
2 共同著作物および・または二次的著作物か
ここまでの内容、すなわち、契約書等の著作物性自体については、少ないながらも裁判例も存在するし、また一部の教科書や概説書でも取り上げられてきた論点である。しかしながら、管見の限り、契約書等の共同著作物性、二次的著作物性については、これまであまり論じられて来なかったように思う。
既にみたように、契約書等が著作物性を認められる余地は、それほど大きなものではない。そのため、そこで議論が終わり、その先に進まなかったのは無理からぬところではある。ただ、仮に(一部ではあっても)契約書等に著作物性が認められるとした場合*11、契約書等の作成過程に照らせば、そこには複数人が関与することが明らかな以上、本来、その共同著作物性や二次的著作物性についても、検討が必要であろう。
2-1 契約書等の作成形態
実際に契約当事者間で締結される契約書等の作成過程は大きく次のように分類できるだろう。
- ほとんどが不動文言となっている、市販のひな形に、対象物・数量・金額・日にちなどの個別条件のみを記載する場合
- 一方当事者が作成した、ほとんどが不動文言となっている契約書案に、対象物・数量・金額・日にちなどの個別条件のみを記載する場合
- 一方当事者が、当該取引のために1から契約書案を起草し、それに対して、相手方が文言の修正を提案し、さらに修正が提案されを繰り返して、完成される場合
- 一方当事者が、自社の既存のひな形を、当該取引のために修正し、それに対して、相手方が文言の修正を提案し、さらに修正が提案されを繰り返して、完成される場合
この内、(1)は市販ひな形作成者の単独著作物であるし、(2)が契約書案作成当事者の単独著作物となることに異論はないだろう。問題は(3)と(4)である。
2-2 共同著作物性
著作権法2条1項12号は、共同著作物を「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と定義する。よって、以下の3要件*12が満足される場合、共同著作物が成立することになる。
- 創作的関与
- 共同性
- 分離利用不可能性
前記(3)のような形で契約書等が作成・修正される場合、通常は、両当事者ともに、表現の創作に関与している(第1要件)といえるであろうし、それが共同して行われていることも異論はないだろう(第2要件)*13。
また、第3要件に関して、分離利用が可能か不可能かは、各人の寄与が、それぞれ独立して著作物と認められる創作的表現と捉えられるか否かによるとする立場をとるならば*14、(3)のような形で作成・修正された契約書等から、それぞれの寄与を取り出しても、それは独立の著作物とは認めがたいであろう。
よって、(3)のような形で作成・修正される契約書等は、共同著作物と考えることができるだろう。
2-3 二次的著作物性
ところで、(4)の場合は、少し複雑になる。この場合、既存のひな形は、あらかじめ(単独)著作物として完成している。
よって、一方当事者が、自社の既存のひな形を、当該取引のために修正してドラフトを作成した場合、それは、既存のひな形を原著作物とする二次的著作物ということになる。
ただ、このドラフトには、相手方の修正も加わって、最終的な契約書等になるであろうから、結局、最終的な契約書等は、共同創作された二次的著作物ということになる。

図で説明すると、まず、図のAが既存のひな形にあたり、この部分は一方当事者が単独で著作権を有することになる。
次に、ひな形に対して、今回の取引のために加えられた変更(もちろん、創作性のあるものに限られる)はBに当たるが、この部分は、両当事者が共同して創作したことになるので、両当事者が著作権を共有することになる*15。
なお、書籍などに掲載されている、契約書等のサンプルを元に、一方当事者がドラフトを作成し、その後数度の修正を経て最終の契約書等に至ったような場合も、基本的な考え方として(4)の場合に近い。ただ、この場合は、書籍に掲載された契約書等のサンプルの作成者(通常、書籍の著作者)が原著作者となり、契約の両当事者は、二次的著作物の共同著作者となる。
2-4 結合著作物性
ところで、ここまでは敢えて言及せずざっくりと検討してきたが、(3)や(4)のようなケースでも、契約書中の全ての条項に相手方による修正が加えられるわけではない。ドラフトのまま修正されない条項も存在する。
そのような条項と、修正(再修正・再々修正・・・)が加わった条項とは本来分けて考えるべきであろう。つまり、前者は、ドラフト作成者による単独著作物である一方、後者は両当事者の共同著作物となるだろう。
結果、契約書全体は、単独著作物である条項と共同著作物である条項から構成されることになる。このような場合、契約書を構成する各条項は、一般的には、分離利用可能であろうから、契約書を全体として、共同著作物と考えることは難しくなる。つまり、契約書全体は、結合著作物と考えざるを得ないであろう*16。
3 職務著作物か
契約書等が著作物だとした場合、それに派生する論点として、その著作者は誰になるのだろうか。言うまでもなく、著作者の探求は、原始的著作権者の特定に必須の作業である。
企業で利用される契約書等の作成・修正作業は、主として、当該企業の法務部員によって行われるであろう。そして法務部員のほとんどは、当該企業の従業員であると思われる。従業員が、職務として、著作物を作成した場合、職務著作が成立する可能性がある。
3-1 職務著作の5要件
著作権法15条は
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
と定めるので、(以下に示す職務著作の)5要件が満足される場合、対象著作物の著作者は実際に創作を行った従業員ではなくて使用者となる。
- 使用者の発意が存在すること
- 業務従事者であること
- 職務上作成されるものであること
- 使用者の著作の名義で公表されるものであること
- 別段の定めがないこと
企業の法務部員が作成・修正する契約書等に関して、第1要件、第2要件*17、第3要件および第5要件が満足されることについては、あまり議論の余地はないだろうから、ここでは詳しく論じない。
3-2 第4要件該当性
問題は第4要件である。というのも、(市販されるひな形を除けば)契約書に、通常の著作物のように、「著作者 ○○」などと表示されることはないからである。一方で、最終的に締結される契約書には、両当事者の名称が、契約当事者として表示される。果たしてこのような表示で、第4要件が満足されたと評価することはできるのだろうか。
この点、著作権法15条は使用者が自己の「著作の名義の下に公表」と定めているのであって、使用者名を「著作者名として表示して公表」と定めているわけではない。また、第4要件は、当該著作物に対する社会的責任の帰属先を明らかにするものとする通説的な理解に照らすならば、厳密な意味の著作者名表示である必要はない。現に裁判例も、第1要件から第3要件が満足される場合には、(広義に見ても著作者名表示とはいえないような形式でも)使用者の名称が表示されていれば、第4要件を満足すると認めている*18。以上を踏まえれば、両当事者の名称が、契約当事者名として表示されることで、第4要件は十分満足されると解すべきであろう*19。
4 まとめにかえて・・・とりあえず
契約書等の著作物性に関する議論だけで、1万2千字にもなってしまった。
つくづく要領の悪いこと・・・
既にみたように、契約書等が著作物となる可能性はあまり高くない。ただ、複雑な契約書等で、その規定ぶりに、作成・修正を行った法務部員に固有の工夫が見られるような場合は、著作物に該当することは否定できない。
その(ような例外的な)場合、個々の条項は、①ドラフトを作成した契約当事者の単独著作物、②契約の両当事者による共同創作にかかる二次的著作物の、いずれかに大別されると共に、契約書全体は、結合著作物となる。
なお、企業の法務部員が作成・修正する契約書等には、基本的に職務著作が成立し、その著作者は、(前記①の場合は)ドラフトを作成した契約当事者である企業、(②の場合は)契約の当事者となる両企業ということになる。
著作物性の検討がすんだ後は、本来なら、その利用が著作権侵害となるか否かを検討しなければいけない。例えば、リーガルテックの文脈では、契約書をスキャンして、電子化することは複製権の侵害にならないのか。また、電子化したファイルを、社内LANのサーバーに保存しておくこと、また社員がそれを閲覧することは、公衆送信権の侵害を構成しないのか。さらに言えば、AIに契約書を学習させることは、学習の結果AIが生成した契約書案と学習対象であった契約書等との関係は・・・などなど。
これらについては、稿を改めて検討したい。
もっとも、著作物性が認められることが少ないと思われるので、これらの点を検討する実益があるのか、そもそも疑問かも知れませんが・・・
なんとか12月9日中にアップできて、ホーッ (^^;)